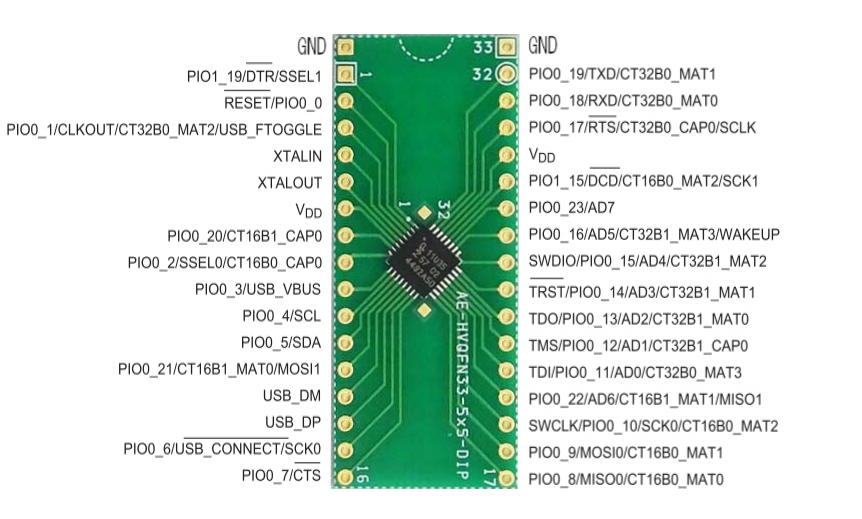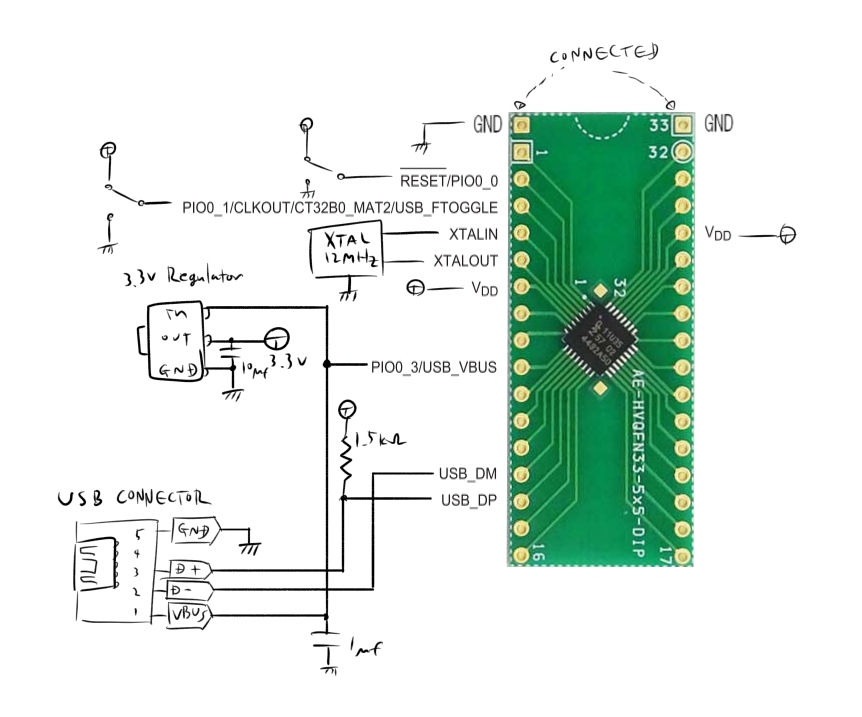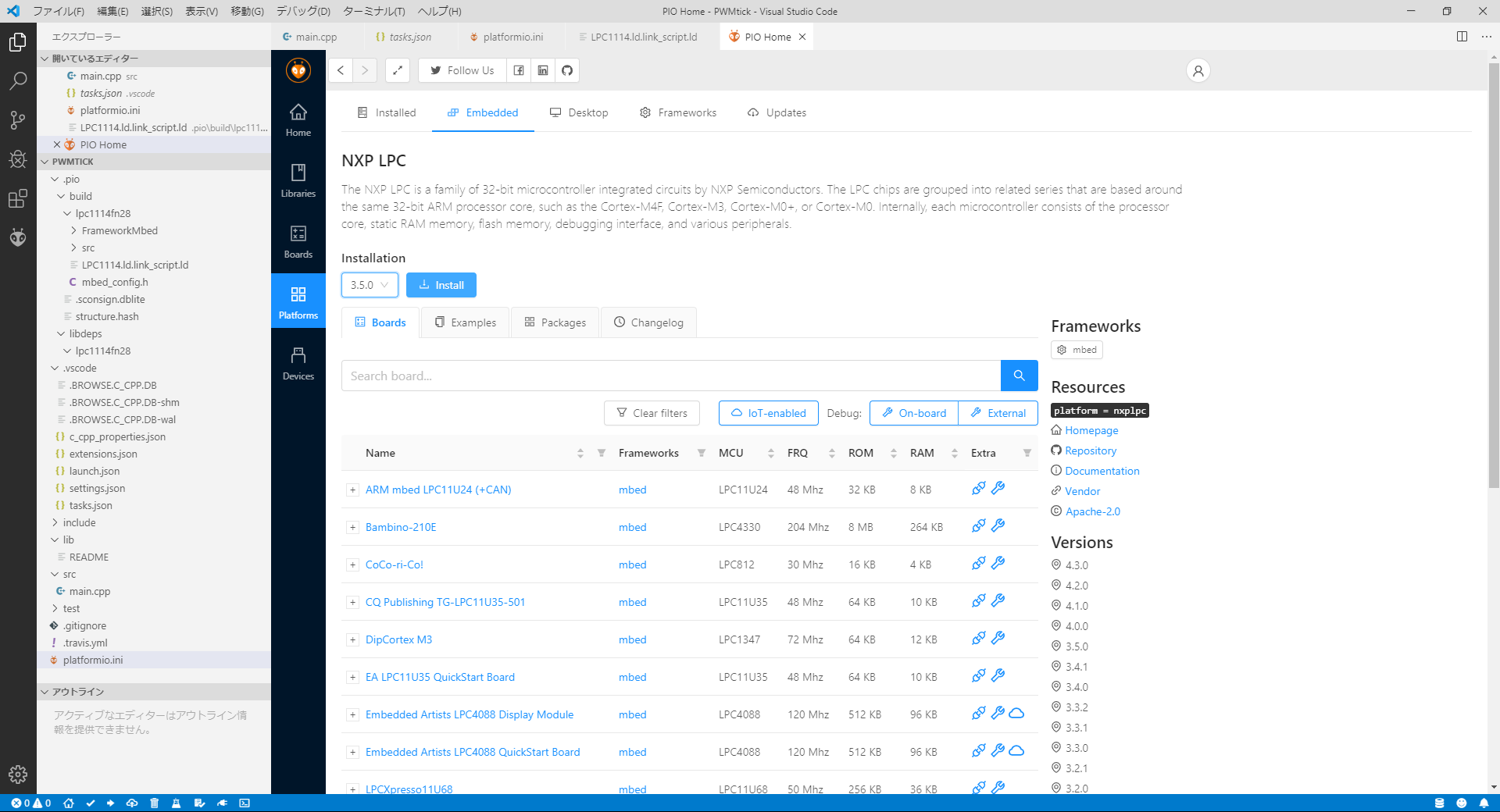期待の超新星
AOM-5024L-HD-R、以下AOM5024。
エレクトレットコンデンサマイクのカプセルで、おひとつ350~500円ほど。
~数個で買うなら送料を考えるとマルツが安いかな。単位大きいならDigikeyとかが安い。
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/27039172/
こいつは個人が買えるカプセルの中で最高のSN比80dBを誇る。
これは数値だけなら3dio Freespace、通称白耳に搭載されているEM-172と同等の性能だ。
しかしPrimoの野郎はこれら高品質なカプセルを一般向けに卸していない為、SN比80dBを叩き出すならこの製品しか無いということになる。
ネットで探してもこのAOM5024を使った例は無かったため、ざっくり触ってみたレポを書いてみる。